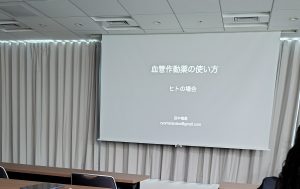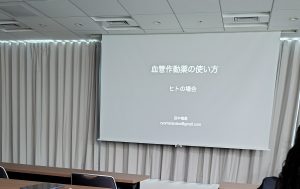こんにちは、獣医師のあさぬまです。
最近温かい日が多いですね☀
東京では季節外れの桜が咲いたらしいです🌸
このまま温かい日が続くといいですが、冬らしい冬も楽しみなので、悩ましいですね…。
さて、先日品川で行われたVESの年次大会に参加してきました。
VESは主に、麻酔や循環、集中管理を中心に検討や研鑽を行っている団体です。
今回のテーマは『循環』でした。
『循環』とは、心臓から始まり、全身をめぐって、また心臓に戻ってくるという一連の流れです。
循環が悪いことを、『ショック』といいます。
よく、ショック=低血圧。と誤解されますが、
『ショック』とは、全身の臓器に必要とされている量の血液や酸素が届かないことを言います。
全身の臓器に血液や酸素を届けることを『灌流(かんりゅう)』というのですが、
難しく言うと、『ショック』=『灌流不全』ということです。
ショックの状態では、全身の臓器傷害が起こる為、その状態が続くことは
死亡率が高い非常に危険な状態です。
今回の年次大会の午前中の講義では、人医療で非常に活躍している医師から、
ショックの概念や、治療方針の決め方などをレクチャーしていただきました!
ショック状態の動物を診察した場合、
①輸液
②昇圧剤(血圧をあげる薬)
③強心剤(心臓を強く動かす薬)
などを用いて、灌流が維持されるようにしていきます。
ただし、どの薬をどのくらい使えば、灌流が維持できるのかは、その子で異なります。
そのため、血液検査、画像検査、動物の見た目や尿の量などを観察し、
適切な量の薬を決めることが大切です。
また、決めた量が適切かどうか常に確認し、調節することが大切です。
午後の講義では、
心疾患をもつ動物に対する麻酔を学んできました。
動物で多く遭遇する心疾患は
①犬の僧帽弁閉鎖不全症
②犬の肺高血圧症
③猫の心筋症
です。
これらの麻酔では、麻酔中はもちろんですが、麻酔後に心不全を発症することがあるので
注意が必要です。
重症の子の治療も、心疾患を持つ子の麻酔も、難しいことが多く、
マンパワーも、設備や経験値も少ない動物の医療では、すべてがうまくいくとは限らないです。
ただ、それでも、日夜、少しでも動物の救命率をあげ、元気に帰ってくれることを祈って、
勉強や治療に励みたいと思います!