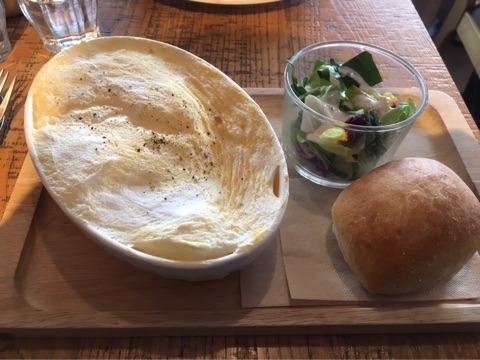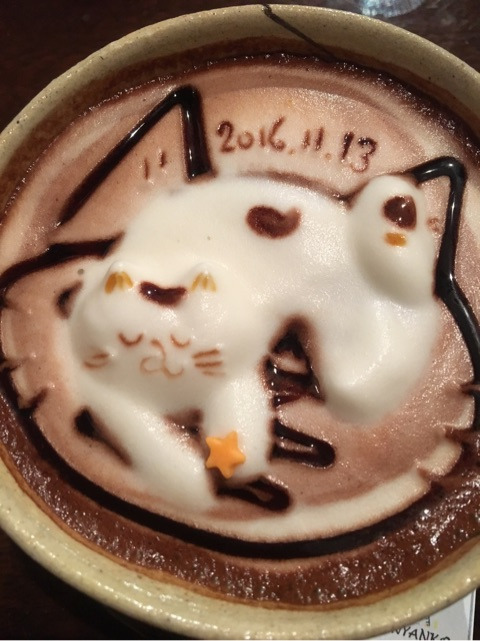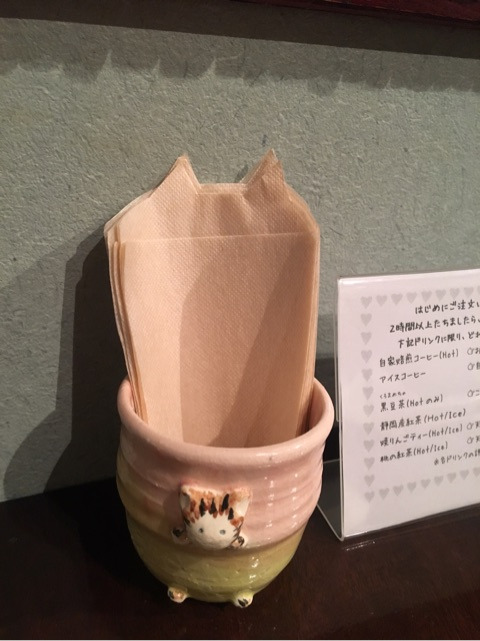2017/04/22
2017年04月22日
こんにちは。
看護師の菅野です!
4月になり暖かい日も多くなる中、風邪を引いてしまいました。
今年はインフルエンザもまだ流行ってるそうなので皆さんも体調管理にお気をつけ下さい(o^^o)
先日メリアルジャパンの社員による「ノミ、マダニ、フィラリア」の院内セミナーを開催して頂きました。
ライフサイクルや病害と予防についてお話しして頂きました!
★ノミ
ノミは、通常1.0日~6日間で卵からふ化して幼虫になり、2度の脱皮をした後、さなぎから成虫になります。ノミの成虫は、光や熱、二酸化炭素に反応して動物の体表に寄生します。寄生すると8分以内に吸血を開始し、24時間~48時間以内に産卵します。その後も体表上にとどまり、吸血と産卵をくり返し通常1~2カ月で一生を終えます。ノミの成虫が犬・猫の体表で過ごすのは、生涯で見るとほんの一瞬にすぎません。多くは犬・猫の周囲(飼育環境)で過ごしています。
ノミは体表に5匹いたらその環境中には95匹いるといわれています。
★ダニ
マダニは、幼ダニ期から若ダニ期にかけて2度の脱皮をへて成長し、成ダニ期を迎えます。発育期ごとに異なる宿主動物へ寄生・吸血するマダニを「3宿主性マダニ」と呼び、すべてのマダニ種のうちのほとんどが3宿主性マダニです。一生の中で吸血する期間は20~25日間ほどといわれ、他の期間は脱皮や産卵、動物へ寄生する機会を待ちながら自然環境のなかで生活しています。
マダニは9〜10月が1番多い時期です!
マダニは命にかかわるSFTS重症熱性血小板減少症候群という危ない病気を媒介します。
症状
1.38度以上の発熱
2.消化器症状(嘔吐、腹痛、下痢など)
3.白血球減少
4.血小板減少
5.AST,ALT.LDH上昇
6.他に明らかな原因がない
7.集中治療を要する
★犬フィラリア症
フィラリアは、蚊の吸血によって犬の体内に侵入し、約6~7カ月で幼虫から成虫に成長します。フィラリアが成虫となり、犬の肺動脈に寄生すると、深刻な症状を起こすようになります。
★症状
慢性犬糸状虫症
疲れやすくなり散歩などの運動を嫌がります。興奮したときや早朝などに乾いた咳をするほか、かっ血、呼吸困難、腹水、ネフローゼ症候群などが現れます。
大動脈症候群
突発性の虚脱、血色素尿、貧血、呼吸困難などの症状がみられます。
フィラリアはしっかり予防を行なっていれば100%
皆さんのお家の子もしっかり予防をしてあげて下さい!
先日桜が満開の時に病院の看板娘ルカちゃんと桜の写真を撮りました。
ルカさんなかなか前を向いてくれず周りをキョロキョロ気にするばかり。
でもそこはルカさん!決める時はいい顔頂きました!