「猫の飼い方」セミナー
2019年04月25日
こんにちは。看護師の金原です。
先日院内で「猫の飼い方」をテーマに飼い主さんセミナーを開催しました。
猫ちゃん達はトイレの形、猫砂の種類などにも好みがありそれによりストレスがかかることも。
まずは違う種類のトイレを2つ置いて少しずつ変えていき好みのトイレを見つけていけるといいですね。

seminar
2019年04月25日
こんにちは。看護師の金原です。
先日院内で「猫の飼い方」をテーマに飼い主さんセミナーを開催しました。
猫ちゃん達はトイレの形、猫砂の種類などにも好みがありそれによりストレスがかかることも。
まずは違う種類のトイレを2つ置いて少しずつ変えていき好みのトイレを見つけていけるといいですね。

2019年04月17日
こんにちは!獣医師の永島です。
先日、内科学に詳しい先生の肝炎について特筆したセミナーを受講しました。
遺伝性に銅が蓄積しやすく歳を重ねる毎に肝炎になりやすい犬種もいます。ドーベルマンやラブラドールなどは特に気を付けたいです。
添付写真はシャチです。鴨川シーワールドへ行ってきました!
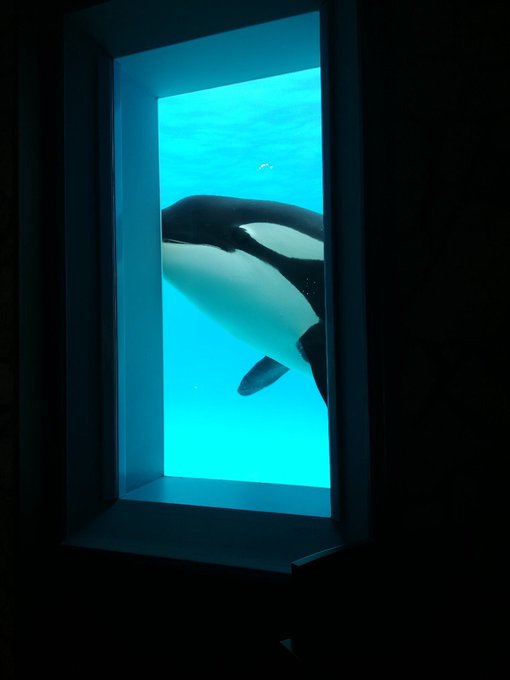
2019年04月15日
こんにちは!トリマー木村です。
今日も師匠の所でカットのトレーニングでした。
マルチーズとトイプードルのカット、特にマルチーズは毛を揃えるのに時間がかかり、難しい犬種です。これからも修業が必要だと痛感しました。
お昼休みに切った毛で遊びました。皆上手。

2019年04月09日
こんにちは!トリマー木村です。
昨日も師匠のところへカットのトレーニングに行ってきました。”なんかかっこいい”、”なんか可愛い”が作れるようにこれからも頑張ります。
全然関係ないのですが、最近家庭菜園を少しずつはじめました。

2019年04月05日
こんにちは、獣医師の浅沼です。
先日、整形外科のセミナーに参加してきました。
今回のテーマは椎間板ヘルニア、人と動物の違いや、治療方針などを学んできました。適切な治療にはきちんとした知識と技術が必要だと再認識しました。
セミナーの帰り道、きれいな桜に出会いました。春を感じる瞬間。

2019年04月05日
こんにちは、獣医師の松井です。
臨床病理セミナーに参加してきました。血液検査結果を読み取ったり、採取された細胞の形態チェックをすることで診断つなげていく分野で、毎月学習させてもらってます。
写真は先日、行った千葉動物公園にて!

2019年03月26日
こんにちは。看護師の佐藤です!
先日、院内で飼い主様向けセミナー「ダックスフンドセミナー」を開催させていただきました。
ダックスフンドの魅力やダックスフンドに多い病気についてお話した後、ミニゲームを行ってミニゲームで1位になった子にはちょっとしたプレゼントをさせていただきました。
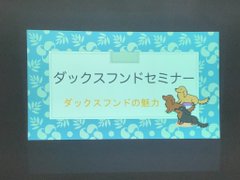
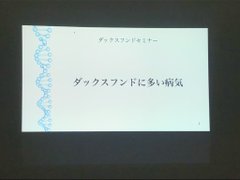


2019年03月20日
こんにちは。看護師の鈴木です。
ビルバックの方が病院向けにセミナーを行ってくださいました!
腎臓病のわんちゃん、猫ちゃんのための液体サプリメント”プロネフラ”です!
腎臓病サプリメントとしての効果に加え、食欲の落ちている子でもよく食べてくれるような味付けになっています。

2019年03月11日
こんにちは!
獣医師の石井です。
先日、細胞診のセミナーに行ってきました。
今回は、肝臓や腎臓など、お腹の中の臓器の細胞診を勉強してきました。
細胞診は判断が難しいものが多いですが、少しでも診断のお役に立てるように頑張って勉強したいと思います!!
2019年03月09日
こんにちは!トリマー木村です。
先日院内で皮膚科専門医の村山信雄先生による皮膚科セミナーが開催されました。
薬浴の仕方やアトピー性皮膚炎についての内容でした。ドライシャンプーのオーツスポットフォームを塗ると、皮膚の痒みがおさまることがある!などたくさん情報を教えていただきました。