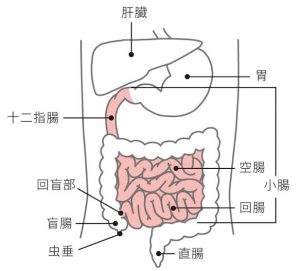眼科セミナー
2023年03月03日
こんにちは、看護スタッフの石井です🐱
今日は毎月眼科の専門外来に来て頂いている寺門先生の眼科セミナーを受講しました。👀
今回のテーマは「ぶどう膜炎」でした。
ぶどう膜とは目の構造で虹彩・毛様体・脈絡膜の3つを総称した名前です。それぞれの部分で起こっている炎症に対して名前が変わってきます。
ぶどう膜炎の症状としては充血、瞳孔の縮瞳、痛み、流涙、蓄膿、前房出血、眼圧の低下などがあります。
充血には2種類あり、結膜充血という白目の部分の血管が充血していて一般的に見る白目の中に血管が走っているものです。もう1つが毛様充血で結膜血管の間の充血のことを言います。結膜充血より深い所の血管が充血するため、表面からは確認ができないそうです。
また、飼い主様がよく目が痛そうにしているという主訴で来院されますが、その痛み・しょぼつきにも区別があります。眼瞼痙攣と羞明があり、眼瞼痙攣は痛みによりまぶたがピクピクしていることで、動物は目の痛みがあると判断できます。羞明は光が当たった時に強く眩しがる事を指し、失明している子などには起きません。もし目が見えない子が目をしょぼしょぼしている時は痛みからの眼瞼痙攣かもしれません。
目と言っても色んな症状、病気があるのでとても興味深い内容でした!また次回も楽しみにしております😊