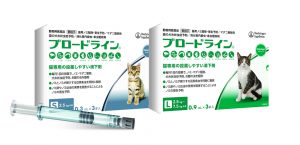1on1セミナー
2021年04月24日
こんにちは、看護師の田村です!
毎月行なっている1on1セミナーに参加させていただきました。今回はスタッフと行った面談をセミナーに参加させていただいているスタッフ同士でフィードバックをしました。初めての試みでしたがそれぞれが良い点と改善点に気づき発表し合うことができていたと思います。
講師の先生よりあった今回のフィードバックとして、
・課題の提案があったら確実にできる課題の選択を促す
・「〜を意識します」は実行できる確率が低くなるので具体的な行動に落とし込む
・他者との比較は明確な意図か無いと優越感や惨めさに繋がりかねないので過去の自分との比較が変化も伝えやすく良い
・課題を全てやるのは難しいのでいくつか特定して取り組む
・基本的は相手から考えを引き出す。提案することも良いが、必ずやるかやらないかの確認をする
以上のような事をフィードバックしていただきました。
最終回となる今回、最後に先生から学んだことは、「リーダーシップを取る者がいかにフォロワーを作るか。最初のフォロワーがどんどんどん周囲に広げていく」です。まずは行動を起こし周囲を仲間にしていきます。最初の一人目の
フォロワーが出てくるとそのフォロワーを筆頭に周囲にも連鎖していきます。この連鎖によりみんなが一つとなって目標に進むことができるようになります。
役半年間に渡り色々な事を学ぶことができました。今後もスタッフ一人一人としっかり時間を取りそれぞれがレベルアップできるよう取り組んでいきたいと思います。