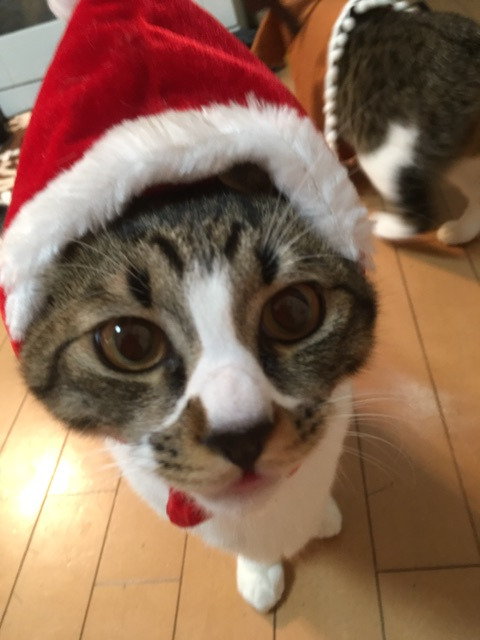こんにちは!トリマー山本です。
11月に入りましたもみじ今年もあと2カ月
時間が経つのはあっという間ですね。
昨日、当院のスタッフ全員を対象とした
院内皮膚科セミナーか゜ありました。
今回のテーマは
『脱毛症へのアプローチ~診断と治療~』
生えろ!抜け毛
ということでトリミングでも身近な抜け毛についてです。
抜け毛の理由は大きく分けて二つあります。
一つは“かゆみ”による抜け毛です。
皮膚がかゆいと感じるとそこを舐めたりかじったり、引っ掻いたりすることで抜け毛や切れ毛が目立つようになります。
そしてプツプツ赤い湿疹がてきたり毛穴に炎症がおきて感染症になることがあります
そしてもう一つが“換毛の異常です”換毛とは毛が生え変わることを言います。
換毛の異常で代表的なのが私も大好きな柴犬です犬
元々外で飼われていた柴犬には夏毛と冬毛があります。
冬の寒い時期にはもこもこのアンダーコートがたくさん生えて
暑い夏にはアンダーコートがごそっと抜けて
風通しのいいオーバーコートが生えます。
ですが、お家の中で生活する柴ちゃんたちはずっと夏毛になっていることが多く
一年中ポロポロ毛が抜け続け、うまく換毛ができなくなっているため
「うちの子は冬なのに毛が薄いガーンアセアセ」
といった生活環境の変化で換毛に異常がでている場合があります。
心配な方は先生に診てもらうこともらって検査をすることもできます!
“かゆみ”にも“換毛の異常”にも当てはまらないけど
毛が抜けてしまうのは毛周期が停止しているかもしれません
毛周期停止になりやすい犬種は代表的なのが
ポメラニアン、シベリアンハスキー、アラスカンマラミュートをはじめ
Tプードル、チワワ、パピヨン、Mダックス等です。どの年齢どの性別でも見られます。
毛周期停止はまず太ももの裏と首の脱毛から始まります。
それからわき腹、後ろ足と毛が抜けていき
ほぼお顔と足先にのみ毛が残っている状態になります。
毛は抜けるけど元気はある、体調に変わりがないのも毛周期停止の大きな特徴です。
またちなみに、トリミングでバリカンを使ったサマーカットにしてから
毛が生えなくなってしまったえーんアセアセという例がよくありますが
これが直接毛周期停止に関係しているかどうかは
よくはわかっていないそうです。
また、マズル(目と鼻の間)の長い子よりも
短い子の方が毛周期停止になりやすいそうです!
私もトリマーとして沢山のワンちゃんの美容のお手伝いをしています
その中でも子犬ちゃんととポメちゃんのサマーカットは絶対にオススメできません。
特にマズルの短いよく“たぬき顔”と言われるポメちゃん達はバリカンを使わずハサミで短くサマーカットにしても毛質が変わってしまったり毛が伸びなくなってしまうことがほとんどです。
ワンちゃんのカットのスタイルも私たちトリマーと一緒に考えましょう。脱毛で悩んでいる方、抜け毛がきになる方一度ミズノで検査をしてみてください
シャンプー、マイクロバブルで改善できることもあります・
少しでも心配がある方は獣医師の先生、看護師さん、トリマーにご相談下さい。
先日友達とディズニーランドに行ってきました。
ハロウィン期間ということでディズニーキャラクターの仮装をしました。
中にはには本物のキャストさんみたいに完璧な仮装をしている人もいました。
とっても楽しかったです